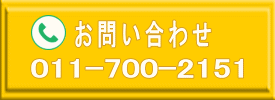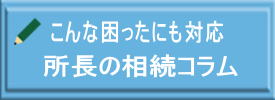���������͎D�y�E�����葱�����k���ւ��C��������
�d�b�ł̂��₢���킹��TEL.011-700-2151
��060-0809 �D�y�s�k��k�X�𐼂S���ڂV�|�S �G�����r���P�O�e
���������̂����k�͂����ڂ�
���������͂܂����k���鎖����ł��B
��������������ɂ͒��ӂ��邱�Ƃ�����܂�
���������Ƃ́A�ƒ�ٔ����ɑ��������̐\���Ă�����葱���̎��ŁA�\���Ċ��Ԃ́A�������N����������m����������R�����ȓ��ł��B
�i������ɂ���Ă͂��̊��Ԃ��߂��Ă����������̐\�����Ă��\�ȏꍇ������܂��B�����Ă��A�܂���x���Ƃɂ����k�������j
�ƒ�ٔ����ɑ��������̐\��������ƁA���̐\���l�̕��́u�ŏ����瑊���l�ł͂Ȃ������v���ɂȂ邽�߁A�S���Ȃ������Ɏ؋�������ꍇ�A�̐l�Ƃ͌𗬂��ʎ����Ȃ��ւ�肽���Ȃ��ꍇ�A���l�̂Ȃ��s���Y�����Ȃ̂ň�Y�𑊑��������Ȃ��ꍇ���ɂ悭���p����܂��B

�������A���ӂ��Ă������������̂�
�u�����͈�Y�����Ȃ��v�ƌ����ꍇ�ł��B
�悭�u��Y�͂���Ȃ������������v�ƌ�����������܂����A���̏ꍇ�͖@�葊���l�S���ň�Y�������c���s�����Ɂu�����͈�Y�����Ȃ��v�ƈӎv�\�������A�ʂ̑����l����Y�����ƌ����b�����������鎖�ʼn������܂��B
�ƒ�ٔ����ɐ\�����Ă�u���������v�Ƃ͎葱�����قȂ�܂��̂ł����Ӊ������B
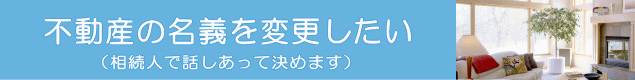
���������̐\���Ă��s���ƁA����܂ő����l����Ȃ��������������l�ɂȂ�ꍇ������A �e���ԂŃg���u���ɂȂ�P�[�X���悭����܂��B
����ł͍���̂ŕ��������������悤�ɂ��A���������̐\���Ă͌�Ŏ����������ł��܂���B
����āA�\���Ă����l���̍ۂ͂܂������������K�v���ǂ����f����K�v������܂��̂ł����߂ɂ����k�������B���k�����ł��B
![]() �@
�@
![]()
�{
����i�\���ɌW��ːЁE�E�؎�㓙�j
���ލ쐬��p�E������ʔ�E�X�������܂݂܂��B
���������̒��ӓ_���m�F���܂��傤
���������̐\����������ۂɁA���ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ���������܂��B
���ɒ��ӂ��Ă������������̂��A�\���Ă͑������N����������m����������R�����ȓ������ł��Ȃ��ƌ������ł����A����͎���ɂ��\�ȏꍇ�����邽��3�������o�߂��Ă���ꍇ���܂������k�������B

���A�B�ɂ��Ăł����A�Ⴆ�Ε��e�����S�����ꍇ�A��Ǝq�������l�ł����A�q���S�����������������ꍇ�́A��ƖS���Ȃ��������̑c����A�������͑c���ꂪ�S���Ȃ��Ă���ꍇ�́A���e�̌Z�킪�V�ɖ@�葊���l�ƂȂ�܂��B
��Y�̒��Ɏ؋�������ꍇ���̓g���u���ɂȂ鎖������̂ŁA���ӂ��K�v�ł��B
�܂��C�̂悤�ɁA�؋������������āA�s���Y��a�����������͑�������Ƃ��������ł��܂���B�}�C�i�X�̍��Y���v���X�̍��Y���S�ĕ������鎖�ɂȂ�܂��B
����������������̎����������K�v�ł�
 ��L�̂悤�ɁA���������ɂ͒��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ���������A�ォ������������ł��Ȃ����߁A�\���Ă�����ꍇ�͂��q�l�̏��悭���f��������ōs�������厖�ł��B
��L�̂悤�ɁA���������ɂ͒��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ���������A�ォ������������ł��Ȃ����߁A�\���Ă�����ꍇ�͂��q�l�̏��悭���f��������ōs�������厖�ł��B
���ɁA�������������鎖�Ŗ@�葊���l�̃����o�[���ς��ꍇ�́A���ɑ����l�ƂȂ���ւ̘A����A���̕����������������邩�ǂ����ɂ��Ă̘b���������K�v�ɂȂ�܂��B
���˗��̍ۂ́A���������������ꍇ�ɂǂ��Ȃ邩�������������Ă�����������Ŏ葱����i�߂Ă���܂��B�܂��͑��}�ɂ����k�������B
shop info�D�y�����葱�����k�����
�D�y�E�����葱�����k��
��060-0809
�D�y�s�k��k�X�𐼂S���ڂV-�S�@�G�����r���P�O�e
TEL.011-700-2151
FAX.011-700-2152

���d���A��̂����k���\

��ԑ��k�����{��
���d���̋A��ɂ������k���������܂��悤�A��Ԃ̂����k�������Ă���܂��B���⍇���̍ۂɂ��\���t���������B

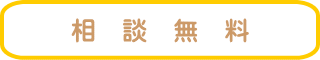

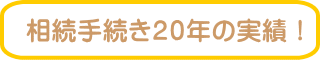 �@�@�@
�@�@�@